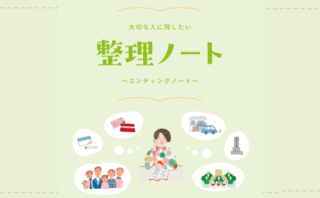これまで、家族や親族が代々守り続ける「お墓」は、当たり前のものとされてきました。けれども、少子化や核家族化、そして価値観の多様化が進む今、「お墓を作らない」「お墓を手放す」という選択をする方が増えています。
今回は、そうした新しい終活のかたちについて、実際に増えている「墓じまい」や、さまざまな供養方法をご紹介します。
お墓にこだわらない供養の考え方
近年では、「通夜や葬儀を行わず、火葬のみで見送る」「お墓を作らず遺骨を引き取らない」といった方法に関心を持つ方も少なくありません。
火葬だけを行い、その後の遺骨は火葬場で管理してもらうという形です。
費用面でも、葬儀やお墓にかかる平均的な費用(およそ400万円)を考えると、「必要最低限の見送り」で遺された家族への負担を減らしたいという思いが背景にあるようです。
ただし、全ての火葬場で対応できるわけではないため、希望する場合は事前に確認することが大切です。
お墓を作る意味と生じる課題
お墓は、故人を偲ぶ大切な場所です。しかし、お墓を作るには墓石代や永代使用料、さらには維持管理費など、まとまった費用がかかります。
加えて、跡継ぎがいない、遠方に住んでいる、年齢的に管理が難しいといった問題もあり、「お墓を建てたけれど維持できない」「将来が不安」と悩む方が増えています。
増えている「墓じまい」という選択
「墓じまい」とは、現在あるお墓を撤去し、管理者に返還することを言います。都市部への人口集中や高齢化が進む中、墓じまいを選ぶご家族が増えているのが現状です。
特に、故郷にお墓があるものの、遠方での生活が続いていてお参りに行けない方や、管理の後継者がいないご家庭では、墓じまいが現実的な選択肢となっています。
墓じまいのあとの供養方法
墓じまいの後、遺骨をどうするかが課題になります。新たな納骨先がある場合は問題ありませんが、そうでない場合は次のような方法があります。
合同墓や納骨堂
- 合同墓:他の方の遺骨と一緒に納める形式。管理は寺院や霊園が行ってくれるため、家族の負担が少なく済みます。
- 納骨堂:建物の中で遺骨を安置する場所。天候に左右されずにお参りできるのが利点です。費用も比較的抑えられます。
自宅での保管・手元供養
遺骨を骨壺に入れ、自宅の仏壇などに保管することも可能です。これは法的にも問題なく認められている方法です。
最近では、遺骨の一部をペンダントなどに加工して持ち歩く「手元供養」も注目されています。故人といつも一緒にいたいという想いを形にする方法として選ばれています。
自然に還る「散骨」という方法
遺骨を粉状にし、海や山などに撒いて自然に還す「散骨」も、選ばれる供養方法のひとつです。
ただし、場所によっては自治体のルールやマナーに注意が必要です。事前に調査を行い、必要があれば専門業者に相談すると安心です。
まとめ
お墓は、大切な家族を偲ぶ場所であると同時に、遺された人にとっての「管理」という現実も伴います。
お墓を作らない、持たないという選択は、家族にとって思いやりある決断になることもあります。
大切なのは、自分や家族にとってどの方法が一番良いかを話し合い、納得したかたちで旅立ちを迎えることです。終活は、「自分らしい生き方の延長線」にある選択でもあるのです。