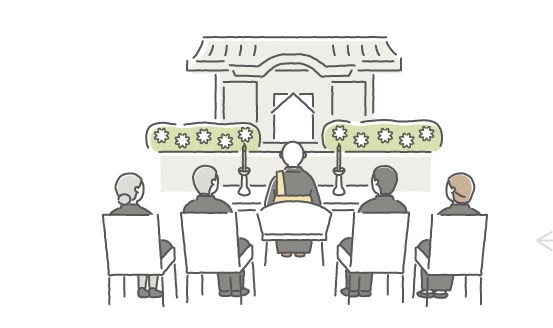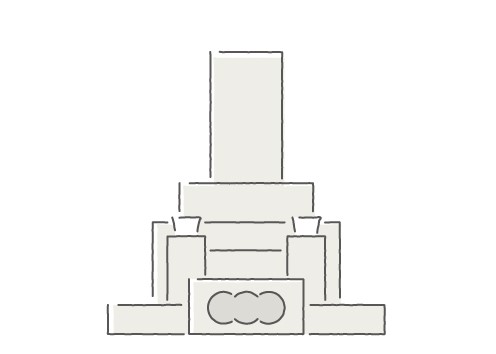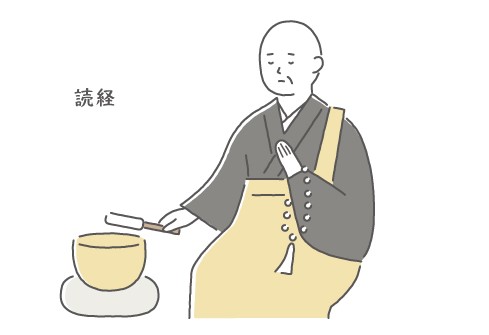施餓鬼(せがき)とは
施餓鬼(せがき)とは、生前に悪行を重ねた結果として餓鬼(がき)という飢えと渇きに苦しむ霊や、無縁仏など供養されない死者に対して、食べ物や供養を施す仏教の行事です。この行事を「施餓鬼会(せがきえ)」または「施餓鬼」と呼びます。施餓鬼は、お布施を与える側と受け取る側の間に身分の差がないという考えから、施食会(せじきえ)とも呼ばれます。
施餓鬼の「餓鬼」とは?
仏教には六道(ろくどう)という輪廻の世界があり、その一つに餓鬼道(がきどう)があります。生前に悪い行いをすると、餓鬼道に落ち、餓鬼という存在になります。餓鬼は常に飢えと喉の渇きに苦しんでおり、こうした餓鬼に対して食べ物などの施しを行うことを施餓鬼と言います。
施餓鬼を行う時期
施餓鬼を行う時期には特に決まりはなく、年に複数回行われることもありますが、お盆の時期に先祖供養とともに行われることが多いです。宗派によっても異なりますが、真言宗や浄土宗、曹洞宗などでは8月のお盆の時期に精霊供養として施餓鬼会が行われることが一般的です。禅宗では施餓鬼は重要な法会とされますが、浄土真宗では死者はすぐに成仏すると考えられているため、施餓鬼は行われません。
まとめ
お寺によっては、施餓鬼の際に檀家同士の交流の場を設けたり、食事を楽しんだり、他のお寺からゲストを呼んで法話をするなどのイベントが行われることもあります。