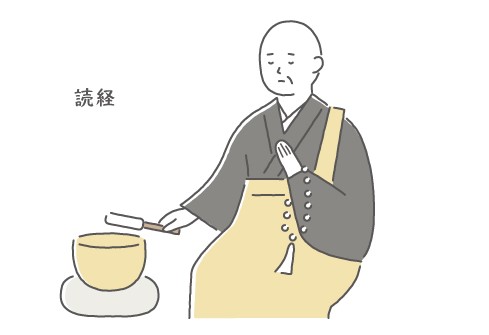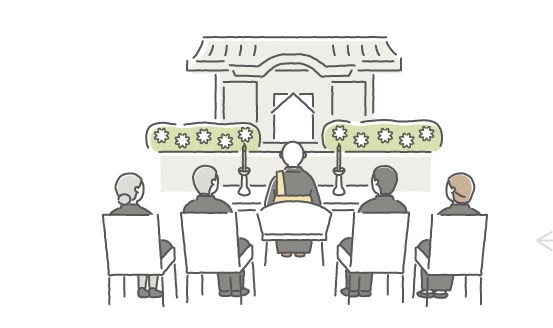導師とは
導師とは、故人の霊を弔うために、葬儀や法要において中心となって読経し、他の僧侶を導く役割を担う僧侶のことです。葬儀を進行し、故人に引導を渡すため「引導僧」とも呼ばれます。
本来、導師とは「導く師」という意味で、仏法を説き、人々を仏道に導く説教者のことを指していました。徳の高い高僧や、仏、菩薩なども仏法を説き導く師として捉えられていました。
住職との違い
住職は「住持職」を縮めた言葉で、一つの寺を管理する最高位の僧侶を指します。お寺の運営や維持管理を行います。一方、導師は葬儀や法要の中心となる僧侶で、出家した僧侶であれば務めることができます。つまり、職業としての僧侶であるかどうかが住職との違いです。
導師の種類と役割
導師には以下の4つの種類があります。
- 大導師:葬儀の全体を統括し、式の進行を管理する僧侶。
- 唱導師:仏の教えを解き、仏道に導く僧侶。また、法会などで率先して読経する役割を担う僧侶。
- 時導師:大きな法要の特定の一部を担当する僧侶。
- 脇導師:大導師に次ぐ高位の僧侶で、住職の資格を持つ必要があり、大導師を補助します。
まとめ
導師を手配する方法は以下の2つです。
- 菩提寺に依頼:先祖代々の墓がある菩提寺に依頼する。
- 葬儀社に依頼:葬儀社に依頼して手配してもらう。
いずれの場合も、参列者の人数や会場の大きさ、予算などを伝えることが重要です。特別な要望がある場合は、事前に葬儀社に相談しましょう。